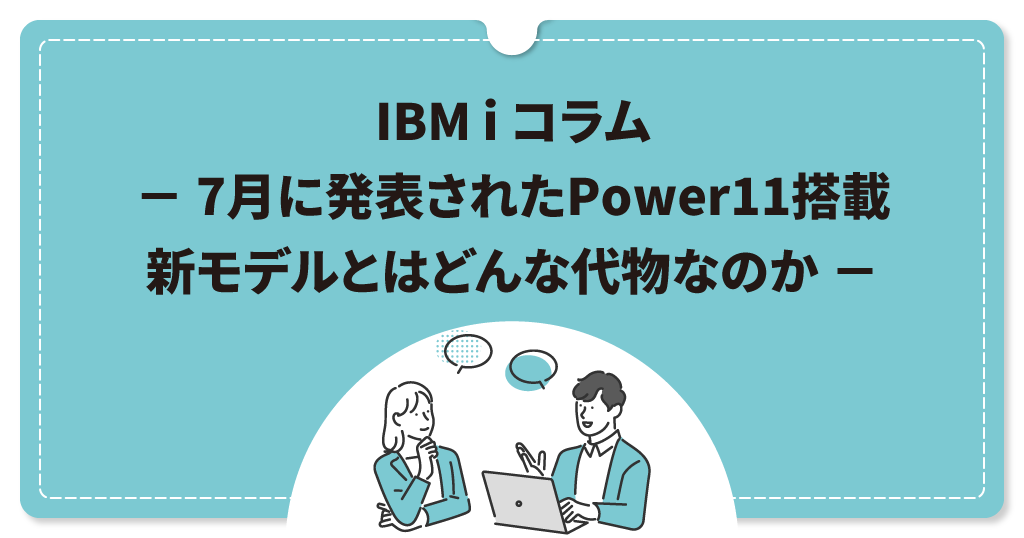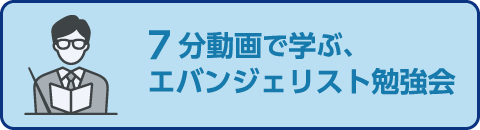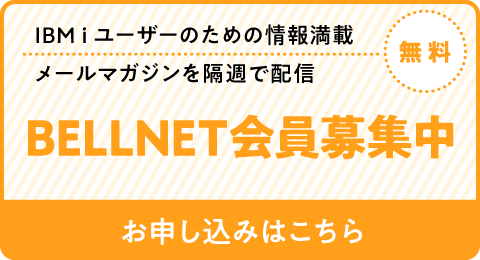IBM i のウンチクを語ろう:その110
- 生成AI狂騒曲 -
皆さん、こんにちは。今回のコラムは何を書こうかと大雑把な構想は先に決まったのですが、少々タイトルに悩んでおりました。自らその渦中にあるにも関わらず、実は自分だけは違っていて高所から眺めているんですよ、といった鼻につくような雰囲気を醸し出すのは本意ではありませんし、そもそもそのような知見を持ち合わせてもおりません。だからといってこのまま流れに乗っているだけで良いのだろうか、という思いもありました。
私は本質的に天邪鬼(あまのじゃく)なので、ブームを目の前にするとどうしても反対側から眺めたくなる本能(?)が疼いてしまい、「やっぱりね」と一人勝手に悦に入ろうとする傾向があることは認めざるを得ません。今回コラムでは、ごく乏しいマーケティングに関する知識をかき集めながら、こんな感じで生成AIブームを眺めることができるのではないだろうか、といったことを、書き連ねてみたいと考えています。一言で述べるならば、生成AIは現在の勢いのままに世界を変えるかもしれないが、現在の機能ではそこまでの威力は発揮できず、次のイノベーションが来るまで一旦休止の時期を迎えるかもしれない、ということです。ただ「予想は外すためにある」という言葉もありますので念のため。
ITにおいては、これまでにも様々なブームがありました。どれほどその登場が華々しく、将来を約束するかのように見えるものであったとしても、成功するものもあれば、一過性のもので終わってしまうケースもあるのが現実です。何がその違いを生むのか、ブームを見ると思い出すのが、ガートナーという調査会社が提唱する「ハイプ・サイクル」です。ハイプ(Hype)とは耳慣れない単語ですが、英和辞典を引いてみると詐欺とか誇大広告といった意味を持っています。このサイクルとは概ね以下のような市場の動きを表現したものです。既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、ここでざっくりとした復習をしておきたいと思います。半分は私自身のためでもあるのですが、お付き合いいただければ幸いです。
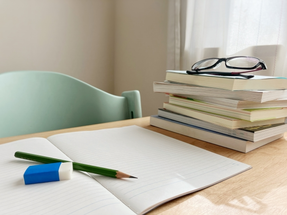
新しいテクノロジーが登場すると、期待が先行しがちな市場の一部がその先進性に好意的に反応して熱狂することがあります。ある程度の情報が行き渡り、次第に課題や問題点が明らかになると、あらゆる期待が無条件に満たされるわけではないことに市場が気付き、新テクノロジーに対する熱気が一気に冷めてしまう時期がやって来ます。そのムードが盛り返すことなく一時の喧騒だけで終わってしまうケースもあれば、明らかになった問題点がクリアされ、再び市場の中で堅調に盛り返し主流派となるケースもあります。ガートナー社のサイトでは、初期の段階から順に「黎明期」「『過剰な期待』のピーク期」「幻滅期」「啓発期」「生産性の安定期」と名付けています。ハイプとは黎明期に展開されるプロモーションが誇大になりがちであることを言っているのでしょう。
では生成AIはどのフェーズにあると考えるのが妥当でしょうか。私が無い知恵を絞るまでもなく、ガートナー社は「生成AIのハイプ・サイクル:2024年」なるものを公開してくれています。生成AIといった大雑把な括りではなく、これをより細分化してそれぞれの位置付けを明らかにしたものです。「大規模言語モデル」とか「プロンプト・エンジニアリング」など30近くあるのですが、そのほとんどは黎明期か過剰な期待のピーク期にあるとされています。実際に市場を眺めてみると、生成AIはモダナイゼーション(テクノロジー刷新)とか人材不足などのあらゆる課題をたちどころに解決するなどといった夢物語のようなものではないにせよ、一歩・半歩でもそれに近づく手段になるのではないか、いった点に多くの方が期待されているようです。
ただ、各種宣伝やメディア報道などを額面通りに受け取れるものなのか、といった点が気になるところです。実際に生成AIを利用する各種サービスにおいても、PoC(Proof of Concept:直訳すると「概念実証」)すなわちテクノロジーが期待通りに使えるものなのか、事前検証を実施するケースは良く聞きます。結果的に採用に至るケースもあれば、そうでないケースもあるのが現実です。不採用の具体的な理由はわかりませんが、期待と現実との間にギャップがあったということです。期待に合わないといった認識が市場の中で積み重なると、幻滅期に向かうことになるのでしょう。先のガートナー社のハイプ・サイクルは2024年7月付け(「As of July 2024」の表記)ですので、1年以上経過した今は幻滅期にさしかかろうとしていると見る方が正しいのかもしれません。

いずれにせよ生成AIの正念場はこれからやって来るはずです。ここで全てのテクノロジーは幻滅期から啓発期に移行できるとは限らない、という点に留意したいと思います。新規登場時に越えるべきハードルがあるとしたら、啓発期に移行して市場で成功するためにはもう一つある、というわけです。この第二のハードルに相当する概念は、コンサルタントのJ.Moore氏によって「キャズム」(Chasm:深い溝)と名付けられていることはご存じの方もいらっしゃるでしょう。同名タイトルの本も有名ですね。ざっくりと概要を知るのであれば、東大IPC社のサイト「キャズム理論とは?キャズムが発生する理由、越えるための7つのポイント」がわかり易いと思います。
何故この「溝」があるのでしょう。市場を大きく2つに分類すると、新テクノロジーを早期に採用したい人で構成される初期市場と、周囲の実績を見ながらやや遅れて採用する人で構成されるメインストリーム市場の、2つが存在することがその理由です。そして経験的に導き出されたものだと思うのですが、初期市場の市場全体に対する構成比は16%だとされています。新テクノロジーが市場の16%程度に普及すればさらなる成長が期待できますが、これに到達することがなければ溝にはまったまま次第に忘れ去られてゆくことになります。
ここで総務省発行「令和6年版情報通信白書」の「第3章デジタルテクノロジーの変遷」の中に記述されている、「AI進展の経緯」に目を向けてみましょう。現在は第3次ブームとされる機械学習の発展形として位置付けられる、生成AIによる第4次ブームにあるとされています。第3次と第4次は連続的なので除外されるとして、これまでに第1次・第2次ブームがあって、その都度「溝」にはまって市場から忘れ去られてきた経緯があるということです。この溝にはまっていた時期は白書では「冬の時代」という言葉で表現されています。コンピュータの演算処理能力に限界があったり、使いこなすための労力が膨大であったりしたことがその理由です。
現在はデータの流通量が飛躍的に増加しており、演算処理能力についてはGPUなどのアクセラレータの登場、さらには人の脳の仕組みを模したニューラル・ネットワークによる自律的な学習機能の実現など、これまでに明らかにされていた「溝」の原因は解決済みと言って良さそうです。一方で件の白書には、偏見やハルシネーション(hallusination:幻覚)をどのようにして排除するのか、個人情報を適正に取り扱えるのか、などといった生成AIの課題が指摘されています。

個人的に生成AIサービスに触れてみて感じるのは、相手は常識知らずの知識オバケのような、表面的にはおとなしくても静かに暴走することのある「猛獣」であるという点です。雑談の相手にするくらいならば、人畜無害なので回答の精度は問題にはならないでしょう。ビジネスの領域においては「猛獣使い」のスキルを身に着けない限り使いこなせないのだとしたら、一部の専門家のためのツールの域を脱しない、すなわち「溝」を越えられず、次の「冬の時代」が来る可能性は否定できないのだと思います。
このスキルとは、人間が何らかの課題を解決しようとする際に生成AIに対して投げ掛ける指示、またはプロンプトの出し方だと言われています。プロンプト・エンジニアリングといういかめしい名前で呼ばれていますね。この壁を突破するための有力なテクノロジーの一つとして最近耳にするのは「エージェント型AI」、もしくは「AIエージェント」です。ホテルで見かける「コンシェルジュ」のようなものだと表現するとしっくりくるかもしれません。人間から課題を受け取ると、生成AIなどを自律的に駆使して望ましい回答を得るように振舞ってくれる、というわけです。課題を適切にエージェントに伝えることは最低限必要になるのだろうとは思いますが、エージェントの出来次第では、ややこしそうなテクニックを気にすることなく、誰もが生成AIを使えるようになると期待されます。
IBM i のプログラミングにおいても、IBM watosonx Code Assistant for i というプロジェクトの名を聞かれたことのある方は多いと思います。当初はプログラムを文章で説明する機能、その後テスト・プログラムを自動生成する機能、文章からコードを自動生成する機能の実現などが視野に入っています。先日来日した開発責任者から聞いたところでは、IBM i 開発部門ではエージェントAI実装に向けた検討を開始するとのことです。具体的な機能とかその実現時期はこれからの決定事項になりますが、特にRPGプログラミングの開発シーンが大きく変化してゆく可能性を感じますね。
ではまた
あわせて読みたい記事

IBM i のウンチクを語ろう:その114
- Code AssistantからProject Bobへ -
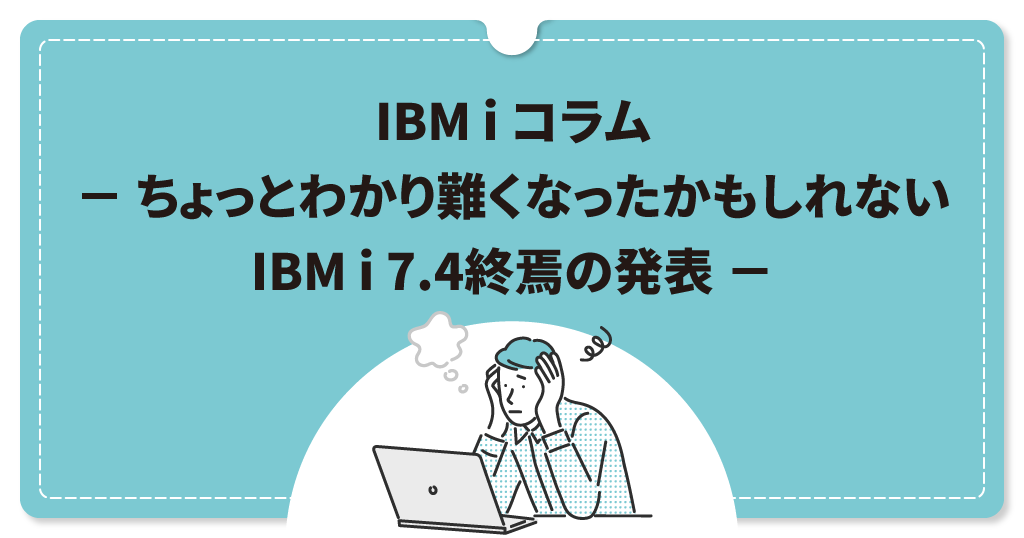
IBM i のウンチクを語ろう:その113
- ちょっとわかり難くなったかもしれないIBM i 7.4終焉の発表 -
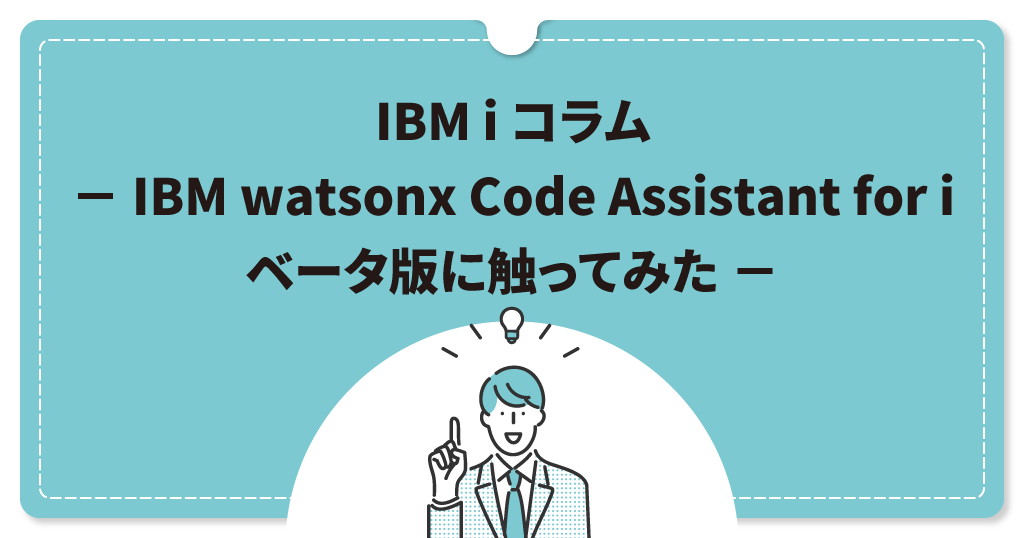
IBM i のウンチクを語ろう:その112
- IBM watsonx Code Assistant for i ベータ版に触ってみた -