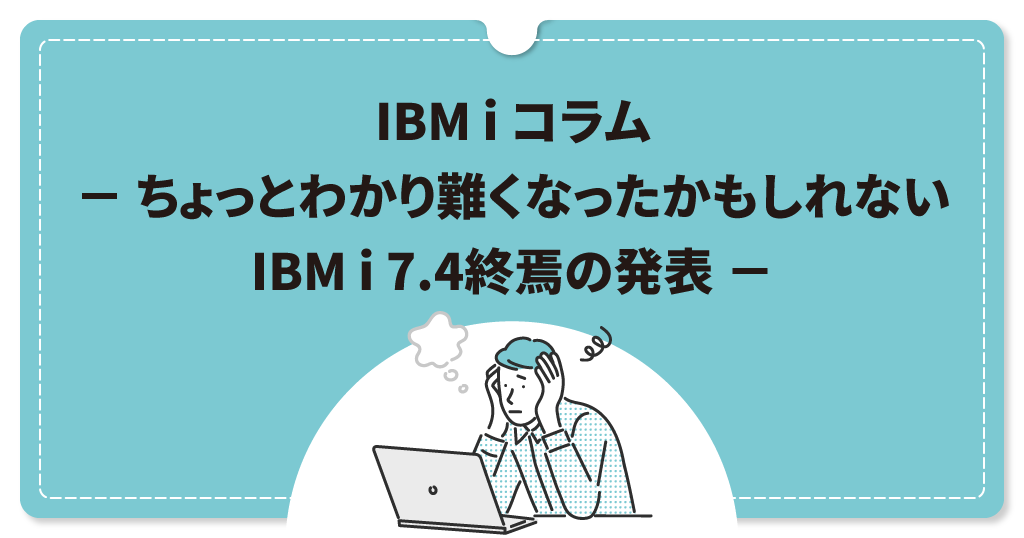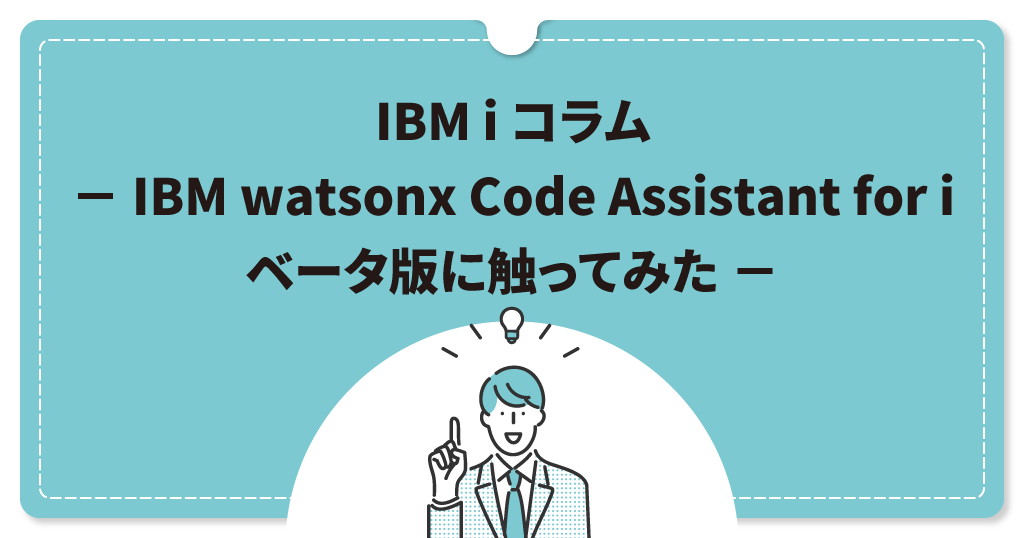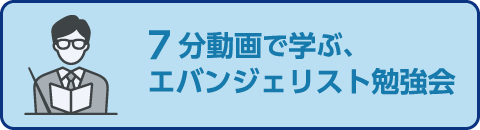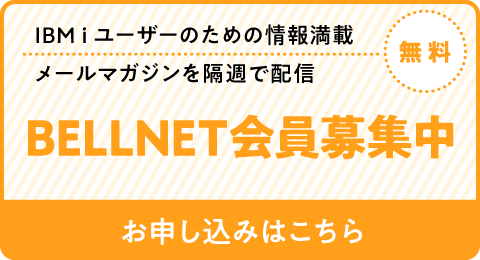IBM i のウンチクを語ろう:その111
- 7月に発表されたPower11搭載新モデルとはどんな代物なのか -
皆さん、こんにちは。先の7月8日に最新Power11プロセッサを搭載するモデル群が発表されたことはご存知と思います。先代のPower10搭載モデルの中で最初に登場したのは2021年9月のE1080でしたから、ほぼ4年ぶりの新テクノロジーの発表です。その後2022年7月にはPower10のモデル・ラインナップが出揃い、さらに2024年5月には追加の小型モデルS1012が続きました。今回のコラムの狙いは、2022年以来3年ぶりに一新されたモデル・ラインナップの概要を、IBM i の視点から眺めてみようというものです。
今回登場したのはIBM i バージョン7.4、7.5、7.6がサポートされるE1180、S1124、S1122の3モデルと、IBM i がサポートされないE1150、L1124、L1122の計6モデルです。それぞれの位置付けを理解するためにも、念のためにモデル表記のルールを確認しておきましょう。最初のEはエンタープライズ・サーバーまたは旧来の言い方だとハイエンド機、Sはスケールアウト・サーバーまたはローエンド機、LはLinux専用機を表しています。次の2桁の数字はプロセッサの世代を表します。Power11搭載だから「11」というわけです。先代モデルではこの部分は「10」になっていましたね。そしてSまたはLモデルにおける下位の2桁はシステムの規模を表しています。十の位は搭載可能なプロセッサのソケット数、一の位はラック搭載時の筐体の高さです。例えばS1124はスケールアウト・サーバー、Power11プロセッサを最大2ソケット搭載可能、筐体の高さは4U(約17.78cm)、と読み解くことができます。極めて機械的にモデル番号が定められているのですね。
さて登場したラインナップのモデル番号を見れば、1ソケットモデルが無いことに気付かれると思います。Power10搭載モデルだとS1012やS1014がありましたが、Power11搭載の1ソケットモデルの登場は少々遅れており、その時期は2026年と想定されています。モデル番号はS1112になるようです。IBM i の料金体系の観点から見れば、プロセッサ・グループP10以上のモデル群は登場したけれどもP05は来年に持ち越されていることを意味します。すなわち当面の間Power10搭載のS1012やS1014は、P05の領域における最新モデルであり続けます。
P05モデルの登場はしばらく待つとして、Power11プロセッサはIBM i の立場から見てどの程度の性能向上が図られているのかを眺めてみたいと思います。IBM i が動作する新しい最小モデルPower S1122を例にとると、8コアで236,400CPWの性能を持ちますので、コアあたり計算すると29,550CPWになります。同様にPower10からPower8までの8コアモデルについて計算すると、以下の表のようにまとめることができます。一番右の列の意味は、コアあたりCPWの観点から、例えばPower S1122は先代のS1014に対して15%の性能向上が図られているということです。Power11モデルはこれまでと比べると、成長の度合いはやや控えめのようです。
| モデル | 型番・型式 | コア | CPW値 | コアあたりCPW | 直前モデル比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power S1122 | 9824-22A | 8 | 236,400 | 29,550 | +15% |
| Power S1014 | 9105-41B | 8 | 205,300 | 25,663 | +68% |
| Power S914 | 9009-41A | 8 | 122,500 | 15,313 | +51% |
| Power S814 | 8286-41A | 8 | 81,050 | 10,131 |
さてPower11プロセッサにもう少し踏み込んでみましょう。プロセッサはチップと呼ばれる金属シリコン片の上に無数のトランジスタやキャパシタを搭載し、パッケージした電子部品です。チップの製造技術7nm(ナノ・メートル)はPower10と変わりませんが、2.5D積層キャパシタなどいくつかの実装技術を取り込むことによってエネルギー効率を高めています。IBMはあまり詳しく説明していないのですが、一般論としてエネルギー効率を高めるということは、電力の多くをプロセッサ上のトランジスタ駆動のために有効に消費でき、発熱という無駄な消費を抑制できることを意味します。そして発熱を抑制できるのであれば、それだけクロックを高めることが可能になります。実際に先代の上記S1014のクロックは3.0-3.9GHzであるのに対して、S1122では3.6-4.0GHzと高速化されており、これがPower11の性能向上の要因なのだと考えられます。
1チップに搭載されているコア数は16あり、これを1つないし2つをパッケージしたものがモジュールとなって基板に装着されます。それぞれ16コアを搭載するSCM(シングル・チップ・モジュール)または32コアを搭載するDCM(デュアル・チップ・モジュール)と呼ばれます。ただしチップあたり16コアというのは物理的最大値であって、品質検査の過程を経ることで、仕様上実際に利用可能になるのは最小4コアから最大16コアまでのバリエーションがあります。
もう一つSCMとDCMのハイブリッドのような、eSCM(「e」は「entry」の意)と呼ばれるモジュールがあります。モジュール内に2つのチップがパッケージされているのですが、2つ目の方の演算用コアは使用されず、データ入出力回路のみが利用されます。同一モジュール内とは言えチップ間の通信には多少ではあってもオーバーヘッドが生じるはずですので、大規模システムにはあまり向いていないのではないかと思います。Power11プロセッサのコスト削減バージョンのようなもので、eSCMを搭載するのはS1122の中でも小規模構成のみであり、S1022sの後継として位置付けられます。より規模の大きなS1122はDCMを搭載し、S1022の後継になります。
S1122について見てみると、モデル番号十の位にあたるソケット数「2」は、システム基板上に2つのモジュールを搭載できるスペースが確保されていることを意味します。すなわち最大搭載モジュール数とソケット数とは同数です。そして最大規模のS1122はDCMを搭載しますので、計算上の搭載コア数は64になりますが、実際に活動状態にあるコア数は60に抑えられています。4コアは活動していない、休止状態にあるということですね。
Power11搭載モデルのセールスポイントの一つはアベイラビリティ(可用性)向上であることは、既にご存知の方もいらっしゃるでしょう。休止状態にあるコアが構成に含まれている、という冗長性もその一つです。中規模以上の構成に限定されますが、これらをスペア・コアとして利用することによって、プロセッサ障害による計画外停止を回避する仕組みが組み込まれています。活動中のコアに障害の予兆が見られた場合は、人手を介することもパフォーマンス上の影響も無いままに、システムのハイパーバイザとファームウェアの働きによって、障害コアが構成から除去され、スペア・コアが構成に組み入れられます。多くの場合、この時にシステムを再スタートさせる必要はありません。S1122の上記例における4コアはこのスペアとして確保されているものです。システムの可用性向上に寄与する仕組みではありますが、完全無停止を保証するものではありませんので、念のため。
参考までに新モデルのプロセッサ構成を以下にまとめておきましょう。ソケット内構成の列における「c」はコア、「+」記号があるものはスペア・コアが存在することを意味します。
| モデル | ソケット内構成 | ソケット数 | コア数 | プロセッサ・グループ |
|---|---|---|---|---|
| S1122 | 4c eSCM | 2 | 8 | P10 |
| 10c eSCM | 2 | 20 | P10 | |
| 16c + 2c DCM | 2 | 32 | P10 | |
| 24c + 2c DCM | 2 | 48 | P10 | |
| 30c + 2c DCM | 2 | 60 | P10 | |
| S1124 | 16c + 2c DCM | 1 / 2 | 16 / 32 | P20 |
| 24c + 2c DCM | 2 | 48 | P30 | |
| 30c + 2c DCM | 2 | 60 | P30 | |
| E1180 | 10c + 1c SCM | 最大構成 : 4 ソケット× 4 ノード |
最大 160 | P30 |
| 12c + 1c SCM | 最大 192 | P30 | ||
| 16c SCM | 最大 256 | P30 |
他の可用性対策ソリューションとして、IBM ConcertというAIを組み込んだ管理インターフェースを通じた自動メンテナンスによって計画停止ゼロを目指すものや、1分以内のランサムウェア検知と迅速な復旧を支援するIBM Cyber Vaultがあります。どちらも個々のお客様のシステム構成を踏まえながらIBMのサービスを前提に実装することになりますので、関心のある方は個別に営業にご相談いただければと思います。
IBMが描くPowerプロセッサのロードマップには、Power FutureとしてPower11の次のテクノロジーが開発途上にあることが示されています。新しいテクノロジーが登場すれば新しいサーバーになり、その一方で「IBM i 7.6の発表の中で注目したいこと」の中で示したように、新しいIBM i のバージョンがリリースされます。IBM i のユーザーにとっては、個々の機能強化もさることながら、メーカーが継続的投資を行っているという事実は最大の安心材料になるのではないかと思います。
ではまた